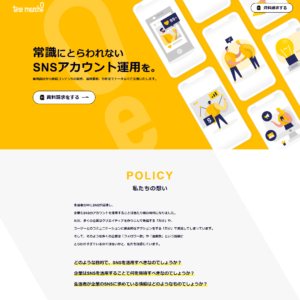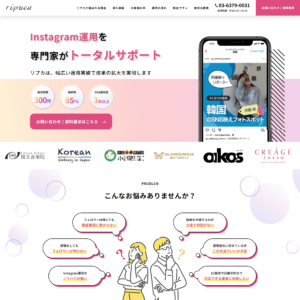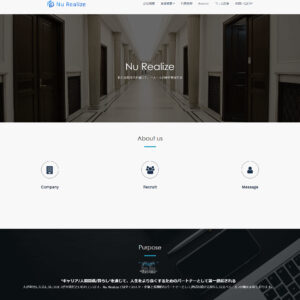採用手法にはいろいろな種類がある?メリット・デメリットも解説!

政治、経済、技術により、社会の変容は働き方や人々の価値観など、さまざまなものを多様化させています。この影響は採用活動の分野も無関係ではありません。そんな中、採用活動で成果を出すためには、多様化している採用手法について、抑えておくことが必要不可欠となります。今回はさまざまな採用手法のメリット・デメリットを解説します。
今採用手法は多様化している
一昔前の就職氷河期においては、人気企業であれば就職希望者が後を絶たず、採用担当者は候補者の中から採用者を選べる立場にありました。
また、働き手側も就職先を選ぶにあたって、給与の高さや知名度、社会的地位の高さなどに基準をおいていました。
ところが現在では企業は人材不足に悩み、働き手の会社選びの基準において、賃金や福利厚生は以前ほど重要視されていません。
就職氷河期といわれる企業が採用者を選べた「買い手市場」時代もあったというのに、なぜ現在は逆転して採用者側が有利な「売り手市場」の状態にあるのかというと、その背景には、少子高齢化問題が絡んでいます。
日本では1970年代に高齢化率が7%を超える「高齢化社会」を迎え、2007年には高齢化率が21%を超え「超高齢社会」にいたるという、世界でも類を見ないハイスピードで高齢化が進んでいます。
原因は団塊世代が一斉に老齢化を迎えたことと、それと同時に後に続く世代の層が薄いことにあります。団塊世代が労働市場から退き、その穴を埋める若い働き手がいないことが、企業における人材不足を招いているのです。
現代では労働者の多くは、企業の価値観が自分の価値観と合致しているか否かを重視するようになり、その価値観の一例として「職場で多様性が尊重されているか」「学習機会は十分に与えられているか」「プライベートな時間を十分に確保できるか」「趣味と両立が可能か」など、経済的な恩恵以上に心の豊かさや自由時間の充実を重視する傾向が増加しています。
人材不足の現在にあって、優秀な人材を確保するためには、企業側が、働き手に対して働きがいを感じられるよう、積極的にアピールをすることが必須です。
これまでの採用方法として定番だった、自社サイトでの募集やハローワークなどの仲介サービスを利用した採用。
縁故採用等に加え、Web求人媒体(転職サイト)サービスを活用した採用、就活・転職イベントへの参加、大学や専門学校の就職課への訪問、インターンシップ制度の導入、求職者を直接スカウトするダイレクトリクルーティング(逆求人)、TwitterやFacebookなどのSNSを活用して、人材採用を図るソーシャルリクルーティングなど「より積極的に人材を確保する」手法が主流となりつつあります。
新卒採用手法を選ぶ際のポイントとは
新卒の人材を確保したい場合に効果的なのは、企業側が求職者をスカウトする「ダイレクトリクルーティング(逆求人)」です。企業は求職者のプロフィールをチェックし、直接アプローチを行います。
この手法のメリットは、従来の方法では応募してもらえなかった優秀な人材に対して、積極的に働きかけることができる点です。逆求人には、イベント型とオンライン型の2種類のサービスがあります。
イベント型では企業側は、ブースを構えた学生からプレゼンテーションを受けます。ターゲットとなる採用候補者と1対1でコミュニケーションをとれることがメリットです。
新型コロナウイルス禍の影響で、対面型イベントの開催数が減少傾向にあることと、イベント時間内でコミュニケーションをとれる学生の数に限りがあることが、デメリットといえるでしょう。
オンライン型では、逆求人を行うサイトに登録した学生のプロフィールをオンライン上から確認します。気になる学生がいたらオファーを送って、自社選考やイベント、面談に参加してもらいます。
メリットはイベント型と比べて、一人あたりの学生にかかる時間が少なく済むこと、プロフィールを確認する時間が限定されていないこと、複数の学生を比較しやすいことなどが挙げられます。
ほかにもターゲットとなる人材のスキルや知識の育成に特化した大学、専門学校の就職課をとおして、採用活動を行う手法も有効です。
就職希望の学生の多くが所属する、学校の就職課を訪問するため、就職活動中の学生に対して求人情報を提供しやすく、スカウトをする場合にもスムーズです。
大学の就職課の利用には、料金がかからないケースが多いのもメリットです。一方で注意したいのは、大学や学部などの特徴が、自社の求める人材と大きくブレないようにすることです。
また複数の大学に対して、求人情報の掲載を依頼する場合、学校訪問の労力や時間が必要なこと、実際に受ける応募数の予想がしづらいことなどにも注意が必要です。
自社に合った採用手法を選ぼう!
少子高齢化により労働市場が売り手市場になったこと、人材確保の場としてオンラインが一般化されたこと、就活場面でSNSツールが活用されていることなどで、採用手法は多様化しました。
優れた人材を確保するために、採用担当者は「待ちの姿勢」から「攻めの姿勢」への変化が求められています。その一方で、多様化する採用手法すべてを取り入れるのは困難です。
自社で効果的な手法を選ぶためには、現在自社が抱えている採用課題と、自社の求める人材要件を明らかにすることが大切です。
また手法によっては、効果があらわれるまで時間がかかるもの、コストが高くつくものなどもあります。
予算や担当者スキルなどを考慮して選考することや、1つの手法に頼らず、複数の採用手法を組み合わせてみることなどが有効です。
まとめ
採用手法の種類と、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介しました。日本では少子高齢化が進み、企業では深刻な労働不足となっています。
労働側の価値観もこれまでの賃金や福利厚生の手厚さ以外に重点を置くようになり、従来の採用手法では、優秀な人材を確保することは困難です。
新卒採用手法においては、逆求人や学校訪問などによる「攻めの姿勢」が効果的です。採用手法によっては、自社に効果がないものもあるため、まずは自社の抱える採用課題と、求める人材像を明確にすることが大切です。